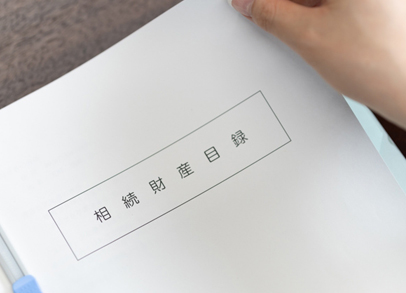
自分が登記上の名義人でない不動産は、自分の財産であることを第三者に証明できず、そのままだと不動産の売却や担保設定などの法的行為ができない。
相続した不動産は相続登記をしないと、相続の権利がある全ての法定相続人の共有財産とみなされてしまうため、自分に所有権があることを主張するには、必ず登記が必要となる。
しかしながら、登記には法定相続人全員からの同意を得なければならず、またそれぞれの実印の押印や戸籍謄本の収集など多くの作業を伴うことになる。
相続が発生して間もない時期であれば、まだ親族が集う機会が多いために、同意を得る機会などをつくりやすいが、年月が経ってくると非常に困難になってくる。その上、自分以外の相続人が高齢となり認知症などのために判断能力が低下してしまったり、転居などで現住所が判明しなかったりと、法的な「同意」を得るための手続きが煩雑となり、膨大な時間とコストがかかってしまうようになるのである。
特に問題となるのが、自分自身以外の相続人が死亡してしまった場合である。
例えば、父親の自宅を長女が相続することについて、長女が母親の面倒を見ることを条件に長男もそれを納得したとする。長男が心変わりする恐れはないと長女が判断し、自宅を引き継ぐことについての書面などは一切交わしていない。従って実際に相続登記をしなくても、しばらく不都合は全く生じなかった。
しかし、長男の死亡によって状況は一変することになる。
長男の妻が自宅の権利を主張してきたのである。
長男の妻が長男から相続できる財産には、父親が残した財産も含まれることになる。自宅の登記の名義人が父親のままであると、長男の妻も自宅を相続財産として受け継ぐことができる余地が残り、長女が「自分が相続することに長男は納得してくれていた」と、いくら説明しても取り合ってはもらえない可能性がある。
土地などの財産を相続する権利を持つ人が増えれば増えるほど、話し合いはまとまらず、それらの所有権を主張することが非常に困難となる。
最後の登記から50年以上経過している土地が日本全国には2割もあるといわれいるが、そうすると、50年以上の時間の経過と共に、その土地の権利関係者は数十人にも及ぶ可能性があり、非常に困難で大きな問題になるリスクを抱えているといえる。
登記の変更手続きがないまま50年以上経過している土地の割合は、大都市部で6.6%、中小都市・中山間地域では実に26.6%となり、特に地方では被相続名義のまま放置されている土地が非常に多い状況である。
相続登記をしなくてもしばらくは不都合が生じないかもしれないが、別の相続人の死亡などをきっかけに問題が発生してくることがあるのである。
土地の権利があいまいになれば、不動産の所有権を違法に移転させる「地面師」の標的になる可能性も高くなる。
自分自身に降りかかるリスクだけでなく、年月が経って世代が代わることで、不動産登記を調べても本来の所有者がわからなくなり、自分の子孫に余計な負担を強いることになりかねない。
また、不動産の存在を相続人が知らず、後々気付いてから遺産の分割協議をやり直して相続税の修正申告をせざるを得ない場合もある。
相続登記をしていない土地の有無を確認し、もし登記が完了していなければ、名義を現実にあわせて変更しておくことが、相続対策において非常に重要なポイントとなる。
